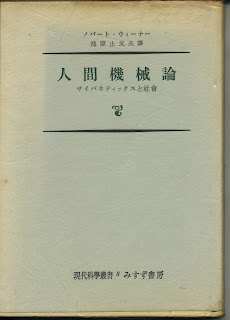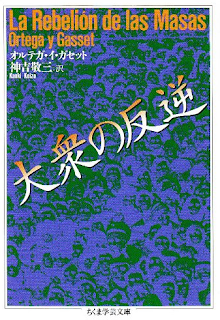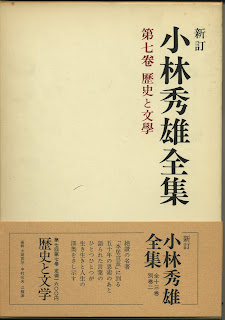オルテガ『大衆の反逆』(10) 疑うことを知らぬ人達
賢者は、自分がつねに愚者になり果てる寸前であることを胆に銘じている。だからこそ、すぐそこまでやって来ている愚劣さから逃れようと努力を続けるのであり、そしてその努力にこそ英知があるのである。これに反して愚者は、自分を疑うということをしない。つまり自分はきわめて分別に富んだ人間だと考えているわけで、そこに、愚者が自らの愚かさの中に腰をすえ安住してしまい、うらやましいほど安閑(あんかん)としていられる理由がある。(オルテガ『大衆の反逆』(ちくま学芸文庫)神吉敬三訳、p. 98) <賢者>は、他者のみならず自己にも疑いの目を向ける。人間は神でない以上、誰にでも間違いを犯す可能性があるからである。が、<愚者>は、他者を疑いなしに否定するが、自らを疑うことはしない。自らが間違っていることなど思いも寄らない。そもそも自らを疑う習慣がないのである。自らを疑わぬ人には、発見もなければ成長もない。ただ与えられたものを大事にしまっておいて、それをそのまま吐き出すだけである。 わたしは大衆人がばかだといっているのではない。それどころか、今日の大衆人は、過去のいかなる時代の大衆人よりも利口であり、多くの知的能力をもっている。(同、 p. 99 ) <大衆>は、知識が豊富であり、その意味で知的水準は決して低くはない。が、問題は、<大衆>は知識獲得の必要は感じても、その知識の歴史来歴にはほとんどといって興味がない。だから<大衆>が持っている知識は、表層的で薄っぺらなのである。「実用」には興味があっても「教養」には関心はない。それが<大衆>というものである。 大衆人は、偶然が彼の中に堆積したきまり文句や偏見や思想の切れ端もしくはまったく内容のない言葉などの在庫品をそっくりそのまま永遠に神聖化してしまい、単純素朴だからとでも考えないかぎり理解しえない大胆さで、あらゆるところで人にそれらを押しつけることであろう。(同) <大衆>は疑うことを知らない。だから正しいことも間違ったことも好悪の篩(ふるい)に掛けられて蓄積される。だから<大衆>の知識は自らのお気に入りに知識であり、正しいか正しくないかは与(あずか)り知らぬことである。したがって、仮に<大衆>の意見の間違いを指摘したとしても、<大衆>にとっては自分のお気に入りが否定されたとしか思われないだろう。<大衆>にあるのは好きか