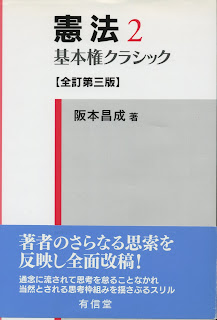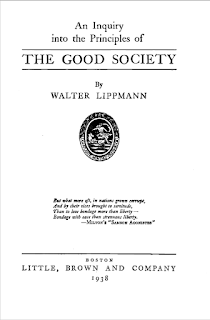ハイエク『隷属への道』(13) 法の支配
個人が各自の判断によって生産的活動を遂行できるような、変動のない法の枠組みを創ることと経済活動を中央集権的に統制することとの間に存在する、これまで述べてきたような違いは、結局のところ、「法の支配」と恣意(しい)的政治との違いという、もっと一般的な差異の一つの特殊例なのである。「法の支配」においては、政府の活動は、諸資源が活用される際の条件を規定したルールを定めることに限定され、その資源が使われる目的に関しては、個人の決定に任される。これに対し、恣意的政治においては、生産手段をどういう特定の目的に使用するかを、政府が指令するのである。(ハイエク『隷属への道』(春秋社)西山千明訳、pp. 92-93) <自由>と<法の支配>は一体のものである。<法の支配>が徹底されていればこそ個人は<自由>に振る舞える。ただし、ここで言うところの<法>とは「自生的秩序」における「法則」( law )を意味するということに注意が必要である。<自由>の獲得の歴史と共に整序されてきた秩序を維持発展することが自由社会には不可欠だということである。 「法の支配」におけるルールは、前もって制定することができ、特定の人々の欲望や必要の充足を問題とするものではない「形式上のルール」となりうる性質のものである。つまり、人々が多様な目的を追求していくための、単なる道具であるようになっている。また、それらのルールは、長期的な規定であるため、いったいどういう人々がそれによって利益を得るかが、決してわからないようなものであり、またそうあらねばならない。ルールを制定することは、特定の必要を満たすための活動なのではなく、むしろルールはそれ自体、一種の生産のための道具そのものである。というのも、それによって人々は、生産活動をしていく上で関わりを持たざるをえない他者が、どのように行動するかを予測できるように助けられるからである。(同、 p. 93 ) <法の支配>は、機会の平等を確保するための「決まり」であり、機会の平等を確保するために予(あらかじ)め示される「共通基盤」である。 集産主義的な経済計画は、当然これとはまったく逆のことを意味する。計画当局は、誰でもいい人々に、どう活用してもいいような機会を与える、というわけにはいかない。当局は、恣意的な活動を禁ずる一般的・形式的なルールに、前もって