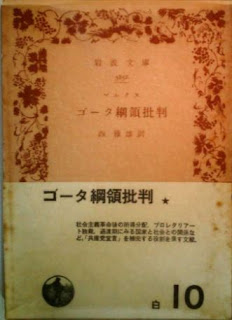ハイエク『隷属への道』(44) 個人を超えた非人格的な力

過去において文明の発展が可能になったのは、市場における「個人を超えた非人格的な諸力」に、人々が身を任せてきたからであり、このことなしに、今日のような高度な文明が発展することは決してありえなかった。言い換えると、われわれの中の誰一人として十分に理解することができないより偉大な何事かを築き上げていくのを、われわれは毎日助けているのだ、という考え方を人々が受け入れてきたからこそ、このように偉大な文明も初めて可能となったのである。(ハイエク『隷属への道』(春秋社)西山千明訳、p. 279) T・S・エリオットも同様の指摘をする。 《詩人は過去についての意識を展開しもしくは把握したうえ、生涯を通じてこの意識を絶えずひろげてゆかねばならない…このようにして詩人は現在あるがままの自己を自分より価値の高いものにいつもまかせきってゆくことが可能になるのだ。芸術家の進歩というのは絶えず自己を犠牲にしてゆくこと、絶えず個性を滅却してゆくことである》(「伝統と個人の才能」:『文芸批評論』(岩波文庫)矢本貞幹訳、 p. 13 ) 過去の人々がそのような考えを受け入れてきたのは、一部の人が今日では迷信とみなしているなんらかの信仰が基礎となっているのか、それとも宗教的な謙遜の精神によるものか、あるいは初期の経済学者たちによる原始的な教えを過大に尊敬したからであったのか、というようなことはここでは問うまい。決定的に大切なことは、細かい働きが誰にも理解できないような諸力に身を任せなければならないということを、合理的に理解することはきわめて困難だということである。それよりはむしろ宗教や経済的教義への尊敬から生まれる、謙虚な畏敬の念に従うことはずっとたやすいものである。(ハイエク、同) 社会の流れに棹差せば助力が得られるのに対し、合理的でないからと社会の流れに逆らえば、「労多くして功少なし」という結果に終わってしまうだろう。 必然性が理解できないようなことが多くあるということこそ、文明の基本的性質なのである。もしも、誰もがすべての必然性を知的に理解しなければならないのであれば、現代の複雑な文明を少なくとも維持していくには、現在いかなる人が持っているよりとてつもなく大きな知性が、すべての人に与えられなければならないだろう。(同、 pp. 279-280 ) <必然性>を理