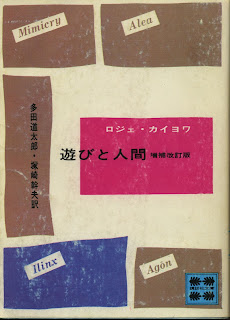ホイジンガ『ホモ・ルーデンス』(43)〈法廷〉なる虚構
古代ゲルマン人の〈民会〉 vierschaar は、まず柵で区画をつくり、その場を祓(はら)いきよめた。こういう法廷は正規の意味をもった魔圏、あるいは遊戯の場、遊戯空間なのであり、その中では人々のあいだの日常普段の階層の差は、一時的に取り払われてしまう。(ホイジンガ『ホモ・ルーデンス』(中央公論社)高橋英夫訳、p. 140) 現代風に言えば、「法の下の平等」ということである。「法の下の平等」とは、日常世界において、人々は平等であると言っているわけではない。〈法廷〉という非日常世界において、日常世界に見られる人種、信条、性別、身分、門地等の差別はすべて取り払われるという意味である。 エッダ『ロキの口論』の中では、ロキは悪口合戦に赴(おもむ)く前に、合戦の行なわれる場所が〈大いなる平和の場〉であるのを、まず確かめた。英国上院は、根本において、今なお1つの〈法廷〉だが、そのため、もともと何らそこに職責のあるわけはない〈大法官席〉が置かれてある。そしてこれは、〈理論的には議院構内の外部〉にあたるとされている。 裁判官は裁きを行なう前に、もう〈日常生活〉の外に踏み出している。彼らは法服を纏(まと)ったり、鬘(かつら)をかぶったりする。この英国の裁判官、弁護士の服装が、これまでにその民族学的な意味について検討されたことがあっただろうか。とにかく私には、それらの服装と17、8世紀の鬘の流行との関係は、どうも本質的なものではないように感じられる。 元来、それは昔の英国の法律家の徴(しるし)であった〈頭巾〉 coif の名残りなのである。この〈頭巾〉は、最初ぴったりと頭からかぶる白い帽子だったもので、それは今日でも、鬘の下の線に、白い小さな縁飾りとなって残されている。しかし、裁判官の鬘はそのかみの官服の遺物という以上のものなのだ。機能の点で、それは未開人の原始舞踊の仮面と、密接な関連があると見られるからだ。それは、着用者を〈別の存在〉に変えてしまうのである。 (ホイジンガ『ホモ・ルーデンス』(中央公論社)高橋英夫訳、 pp. 140f ) たとえ裁判官という肩書が与えられていたとしても、所詮は同じ人間であることに違いない。だから、裁判官は、〈法廷〉という仮装された空間においては、非日常世界を装うに相応しい、鬘を被(かぶ)り、法服を纏(まと)うのである。このよ