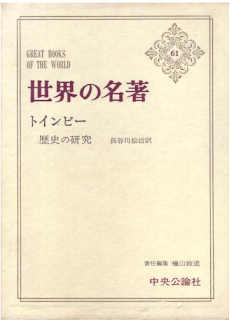ホイジンガ『ホモ・ルーデンス』(104)衰退の一途を辿る遊び
Closely akin to this, if at a slightly deeper psychological level, is the insatiable thirst for trivial recreation and crude sensationalism, the delight in mass-meetings, mass-demonstrations, parades, etc. The club is a very ancient institution, but it is a disaster when whole nations turn into clubs, for these, besides promoting the precious qualities of friendship and loyalty, are also hotbeds of sectarianism, intolerance, suspicion, superciliousness and quick to defend any illusion that flatters self-love or group-consciousness. We have seen great nations losing every shred of honour, all sense of humour, the very idea of decency and fair play. This is not the place to investigate the causes, growth and extent of this world-wide bastardization of culture; the entry of half-educated masses into the international traffic of the mind, the relaxation of morals and the hypertrophy of technics undoubtedly play a large part. -- J. HUIZINGA, Homo Ludens (やや深層の心理水準であれば、これに酷似しているのが、詰まらない娯楽や