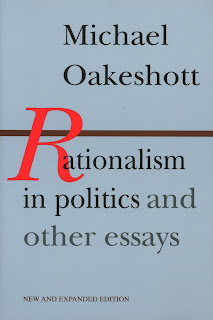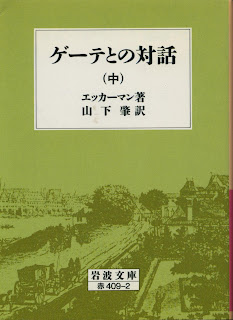オークショット「ホッブズの著作における道徳的生」(21)ホッブズの幼稚な二元論
人は誰でもあらゆる状況において、「自分自身の本性の保全」を求める権利を持っている。(オークショット「ホッブズの著作における道徳的生」(勁草書房)、p. 319) が、このようなことを言っても、<権利>を保障してくれる「存在」がなければ意味がない。例えば、「国家」という存在があって初めて<権利>は保証され得るのである。また、「自分自身の本性の保全」というのも、曖昧模糊(あいまいもこ)としてよく分からない。要は、ホッブズは空想の中を浮遊しているのである。 そしていかなる状況においても、人間はそれ以上のことを求めて努力する(たとえば無用の残酷行為にふけったり首位に立とうと欲したりすることによって)権利など持っていない。(同) 人は「自分自身の本性の保全」を求める権利しか持っていないなどという話もホッブズの勝手な空想である。例えば、「言論・表現の自由」という「自由権」はどうなるのか。そもそも「言論・表現の自由」がないのであれば、ホッブズの主張も越権行為になってしまうだろう。 もし彼が「自分自身の本性の保全」にとって余計なことを求めるならば、彼の努力は自分自身の破滅を求めるものだから、不合理で、非難さるべきで、不正である。(同) 「言論・表現の自由」は、<「自分自身の本性の保全」にとって余計なこと>であろうが、これが<不合理>であったり、<不正>であったりするはずがない。「自分自身の本性の保全」以上のことは、<自分自身の破滅を求めるもの>などというのは、余りにも浅見、浅慮と言わざるを得ない。 しかし自分自身の本性を保全する努力は、すでに見たように、厳密には平和を求めて努力することである。またそれ以上のことを求めることは戦争と自己破壊を求めることである。(同) 「平和」とは、個人的なものではなく社会的なものであろう。一方、<自分自身の本性を保全>とは、個人的なものであろう。ホッブズはこの辺りの位相の違いを混同してしまっている。 ゆえに人は平和を求めるとき正しく、戦争を求めるとき不正である。(同) これも<人>ではなく社会と言うべきであるが、社会が戦うことを選択することは、必ずしも<不正>ではない、詰まり、この問題は優れて「状況依存」的であるということは押さえておかねばならない。例えば、侵略戦争であれば、確かに<不正>の誹(そし)りを